要介護(要支援)認定の申請方法と流れについて
介護保険サービスを利用するには
介護(介護予防)が必要になった方は、町に申請し、「介護や支援が必要な状態である」という要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定を受けることができる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
第2号被保険者の方に該当する方は、老化が原因とされる特定疾病(※)が原因で介護が必要な方で、医療保険に加入している方
(※)特定疾病は以下の16種類が定められています。
⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請方法と流れ
1.ほけん福祉課の窓口または郵送で要介護(要支援)認定申請をしてください。
申請区分
- 新規申請 初めて要介護(要支援)認定を希望する方
- 更新申請 すでに要介護(要支援)認定を受けていて、更新を希望する方
- 区分変更申請 すでに要介護(要支援)認定を受けていて、区分の見直しを希望する方。
申請できる方
- ご本人
- ご家族
- 成年後見人
- 地域包括支援センター
- 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人保健施設、介護保険施設
窓口で申請する場合
受付窓口:いの町1400番地すこやかセンター伊野1階 ほけん福祉課高齢福祉係
必要なもの
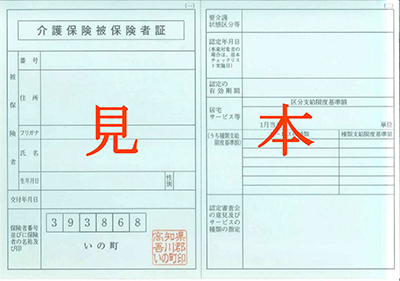
- 65歳以上の方
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての方にお送りしています。紛失された方は再交付申請が必要となりますので窓口でお申し出ください。 - 64歳以下の方
運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認ができる公的な書類
有効期限内の健康保険証
郵送で申請する場合
送り先
〒781-2110 いの町1400番地すこやかセンター伊野内
いの町ほけん福祉課高齢福祉係
※郵送による申請の場合は、到着した日が受付日となります。
郵送していただくもの
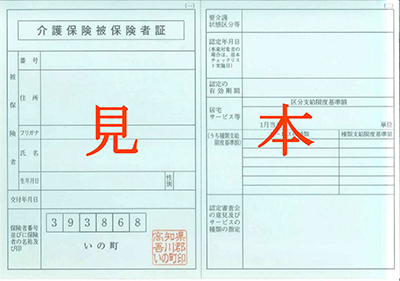
- 65歳以上の方
要介護(要支援)認定申請書
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての方にお送りしています。紛失された方は介護保険被保険者証再交付申請書も同封してください。 - 64歳以下の方
要介護(要支援)認定申請書
介護保険被保険者証交付申請書
運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認ができる公的な書類の写し
有効期限内の健康保険証の写し
申請用紙はこちらからダウンロードして印刷してください。
各種申請書は窓口でも配布しています。
要介護認定の更新手続きについて
- 要介護認定には有効期間があります。有効期間は状態に応じて異なりますが、初回認定後の有効期間は原則6か月です。介護保険サービスを引き続き利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新の申請をしてください。更新申請後、あらためて調査・審査、認定が行われます。
2.認定調査を実施します。
被保険者ご本人の心身の状況を調べるため、ご自宅、または生活している場所(入院先、入所先等)へいの町の介護認定調査員が訪問します。
- 平日の午前10時または午後2時の時間帯で実施します。
- 調査時間の目安は30分から1時間程度です。
- 全国共通の基本調査項目の選択肢を判断します。また、特記事項には、介護にかかる手間と頻度、日中や夜間での状況、具体的な介護行為などを記載していきます。
- ご自宅での調査の場合、特に認知症などで正確な状況を被保険者ご本人が伝えられない場合には、日常生活の様子がわかるご家族に立会いをお願いしています。
- 正確な情報を記録に残すために面談の様子を録音させていただきます。調査目的以外で利用することはありませんのでご了承ください。
- 正しく調査をするために、被保険者ご本人の心身の状態が安定している時に実施します。ショートステイ退所・入院・退院直後など、生活状況が変わった際には1週間経過した後に調査します。手術の前後や発熱時なども調査ができません。
- 状況が変化した場合は、早めにほけん福祉課高齢福祉係までご連絡ください。
3.主治医に意見書の作成を依頼します。
認定調査と並行して、医学的な立場からの意見も判定材料とするため、町から主治医に意見書の作成を依頼します。意見書作成料の自己負担はありませんが、作成するための診察にかかる費用は自己負担となります。作成された意見書は、町へ直接返送されます。
- 要介護(要支援)認定申請書に記入された主治医へ意見書の作成を依頼します。
- 長期間受診していない場合は、現在の心身の状況が反映されないことがありますので、申請前に主治医へご相談ください。
4.要介護認定の一次判定を行います。
訪問調査の結果や、主治医意見書の一部項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
5.介護認定審査会による判定(二次判定)を行います。
一次判定の結果と、訪問調査による特記事項や主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」(※)で審査を行い、「どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)」を判定(二次判定)します。。
(※)介護認定審査会とは
6.認定結果を通知します。
介護認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、介護予防が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の要介護状態区分と、認定の有効期間を記載した認定結果通知書と介護保険被保険者証を送付します。
認定結果により受けられるサービスが異なります。
| 要介護状態区分 | 受けられるサービス | サービスの内容 |
|---|---|---|
| 要介護1から5 | 介護保険の介護サービス (介護給付) |
介護の必要性が高い方を対象に、住みなれたまちや家で自立した生活が送れるよう支援するため、状態の改善・悪化防止を目的に提供するサービスです。 |
| 要支援1または2 | 介護保険の介護予防サービス(予防給付) | 要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い方などに提供するサービスです。 |
| 非該当(自立) | 町が行う介護予防事業 (地域支援事業) |
介護(介護予防)保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している方や、将来的に介護が必要となる可能性が高い方が町の事業を受けられます。 |
認定結果が「要介護(要介護1から5)」または「要支援(要支援1または2)」の方
介護保険サービス等の利用ができます。
介護保険サービスの利用を希望される方へ(チラシ)(PDF形式)
介護保険サービスの利用は、利用者の希望をもとに「いつ」「どんなサービスを」「どれくらい」利用するかをケアマネジャー(※)が決めるサービス計画、「ケアプラン」の作成が必要です。
※ケアマネジャーとは
在宅でサービスを利用したい方
居宅介護支援事業所もしくは小規模多機能型居宅介護支援事業所へ直接依頼してください。ケアプランをケアマネジャーが作成します。
施設に入所してサービスを利用したい方
入所を希望する施設に直接申込してください。ケアプランを施設のケアマネジャーが作成します。
判定結果が「非該当」だった方
判定結果が非該当だった方は、介護保険サービスを利用することはできませんが、いの町では、非該当の方も参加できる介護予防の活動や、自宅でできる運動のご提案、地域の集いの紹介などの支援を行っています。お問い合わせやご相談はいの町地域包括支援センターへご連絡ください。
問い合わせ先
いの町地域包括支援センター
TEL.088-893-0231
吾北総合支所 住民福祉課
TEL.088-867-2300
介護現場におけるハラスメント防止にご協力ください。
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
-
- 088-893-3810
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。





